
使い道のない「いらない土地」を相続して、どうやって手放せばいいのか?と探した結果「国に返す方法」に行き着いた方もいらっしゃるでしょう。
近年は「相続土地国庫帰属制度」のスタートで、いらない土地を国に返すことも可能になりましたが、実態はどうなのでしょうか?
今回は、いらない土地を国に返すための具体的な方法や注意点、返せない場合の代替策まで、分かりやすく解説します。
ただ結論を先に言うと、「相続土地国庫帰属制度」を利用して、相続した「いらない土地」を国に返すためには、さまざまな要件をクリアしなければならず、かなり難しいです。
この制度を時間と労力をかけて利用するくらいなら、専門の買取業者に売却した方がスムーズで簡単すし、断然オトクです。
査定は「完全無料」で、しつこく営業されることもないので、いらない土地を処分したいと考えている人は一度相談してみるといいですよ。
\相続した「いらない土地」を高額買取/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」とは?

相続した土地の管理や維持に悩む人が増えたことを受け、2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
この制度は、一定の条件を満たした土地であれば国に返すことができるという仕組みです。

制度を理解しやすくするために、以下の3つについて説明します。
2. 利用できる人の条件
3. 国に返せる土地と、返せない土地の違い
1. 制度が新設された背景と目的
「相続土地国庫帰属制度」が新設された理由は、管理できない土地が全国的に増加し、所有者不明の土地問題が深刻化していたためです。
人口減少と高齢化で土地を活用できないケースが急増し、放置されたままの土地が社会問題となっています。
たとえば、相続したが使い道がなく、維持費だけかかってしまう土地や、遠方で管理が難しい山林・農地などが典型例です。
また、所有者不明の土地が「公共事業」や「防災対策」の妨げになるなど、国や自治体にとっても大きな課題でした。
このような背景から、不要な土地を一定条件で国が引き取る制度が設けられたのです。
この制度の導入によって、相続人が負担を減らせるだけでなく、社会全体の土地管理にもつながることが期待されています。
2. どんな人が利用できる?
この制度を利用できるのは、基本的に相続や遺贈によって土地を取得した相続人や受遺者です。
なぜなら、この制度は「自分で取得した土地」ではなく、「相続や遺贈により不本意ながら取得した土地」を手放すための救済策だからです。
たとえば、以下のような人が対象になります。
- 両親から地方の土地を相続した人
- 親族の遺産分割で山林を受け継いだ人
- 遺言によって土地を取得した人
一方、自分で購入した土地や、法人が取得した土地は原則として対象外です。
また、共有名義の場合は、共有者全員の同意と申請が必要となる点も注意が必要です。
「相続や遺贈によって取得した個人」がこの制度の対象者であることを覚えておきましょう。
関連記事

3. 国に返せる土地と、返せない土地の違いは?
国に返せる土地には条件があり、すべての土地が対象になるわけではありません。
その理由は、国が引き取ることで過剰な負担や管理リスクが発生しないよう、利用条件を厳格に定めているためです。
たとえば、以下のような土地は申請段階で却下されます。
・汚染や境界紛争のある土地
・担保権が設定されている土地
・通路など公共利用が難しい土地
また、山林や農地でも一定の管理コストやリスクが高い場合は、不承認となることがあります。
一方で、宅地で権利関係がシンプルな土地や、周辺にトラブルがない土地などは国に返せるケースもあります。
このように、返却できるかどうかは土地の状態・権利関係・法令順守など多くの条件をクリアする必要があります。
申請前にしっかり条件を確認し、専門家にも相談しながら進めることが重要です。
\相続した「いらない土地」を高額買取/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
「相続土地国庫帰属制度」の利用条件・対象となる土地

「相続土地国庫帰属制度」を利用して土地を国に返すには、厳しい利用条件をクリアする必要があります。
全ての土地が対象となるわけではなく、制度上のハードルも高めです。

ここでは、申請した時点で却下される土地の具体例と、審査段階で不承認となるケースについて詳しく解説します。
申請時点で却下される土地の例
相続土地国庫帰属制度では、申請した段階で即座に却下されてしまう土地が存在します。
国が管理や処分に大きな負担を強いられる土地は、最初から対象外とされているためです。
先ほども説明した通り、建物や古い倉庫、工作物、樹木などが残っている土地、土壌汚染や埋設物が疑われる土地、境界が不明確で紛争リスクがある土地などは、申請しても却下されます。
さらに、「担保権」や「地役権」など権利関係が複雑な土地、「市街化調整区域」や「公道」として利用されている土地も申請できません。
これらの土地は、国に返す前に自分で建物解体や権利整理などが求められます。
結果的に、「そのままの状態で手放せる土地」は非常に限定的なので、まず自分の土地が該当しないか注意深く確認することが重要です。
関連記事

審査で不承認となるケース
申請後、法務局による審査で不承認となるケースも少なくありません。
その理由は、申請時に問題がなくても、現地調査や詳細な確認によって「新たなリスク」や「管理コスト」が判明することがあるからです。
たとえば、現地調査で隣地との境界争いが発覚したり、法令違反や不法投棄などの問題が見つかったり、申請時に提出した情報と実際の状況が異なったりする場合などが挙げられます。
他にも、土地の形状や周辺環境が「国の管理基準」を満たさないケースや、過去の利用履歴により土壌汚染が疑われるケースなども、不承認の理由になります。
申請が受理されても必ず承認されるとは限らず、最終的な判断は国が慎重に行うため、事前準備と土地の状態確認が不可欠です。
\相続した「いらない土地」を高額買取/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
相続土地国庫帰属制度の費用と必要書類

相続土地国庫帰属制度を利用する際には、事前に必要な費用や書類をしっかり把握しておくことが大切です。

ここでは、申請にかかるコストや準備するべき書類について分かりやすくお伝えします。
審査手数料・負担金はいくらかかる?
相続土地国庫帰属制度では、申請ごとに「審査手数料」と「負担金」が必要です。
これは、制度を維持するためのコストや、安易な申請を防ぐ目的があるためです。
たとえば、1筆あたりの審査手数料は14,000円です。
さらに、承認された場合には負担金として最低20万円程度がかかります。
土地の種別や条件によって金額が変わる場合もあり、山林や農地などは負担金が高額になることも少なくありません。
共有名義の土地では、各共有者ごとに費用が発生する点にも注意しましょう。
こうした費用を見積もったうえで申請を進めることが、手続きのトラブル防止につながります。
関連記事

手続きで必要になる書類一覧
制度の申請には、さまざまな書類を用意する必要があります。
これは、土地の権利や状態を正確に証明し、申請者が適格かどうかを審査するためです。
主な書類は以下のようになります。
・相続関係がわかる除籍謄本
・遺産分割協議書
・登記事項証明書
・不動産の公図や地積測量図
・固定資産税評価証明書
・現地写真 など・・・
土地ごとに必要な資料が異なる場合もあり、境界確認書や専門家による調査報告書が求められるケースもあります。
事前に法務局のガイドラインやチェックリストを活用して、不備や不足のないよう慎重に書類をそろえておくことがスムーズな申請のポイントです。
\相続した「いらない土地」を高額買取/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
相続土地国庫帰属制度の申請から引き渡しまでの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用する際は、各ステップごとに注意点があります。
スムーズに手続きを進めるためには、事前相談から申請、審査、引き渡しまでの流れをしっかり理解しておくことが重要です。

ここでは具体的な4つの手順と、それぞれの段階で押さえるべきポイントを解説します。
1. 事前相談(法務局での相談)
まず、申請前に法務局での事前相談を行うことが推奨されています。
それによって、土地の状況や権利関係、申請の可否について専門家のアドバイスが受けられ、無駄な申請を避けられるからです。
たとえば、土地の条件が制度の基準を満たしているか、必要な書類に不備がないか、共有名義の場合の手順などを、法務局職員と確認できます。
実際に、事前相談を経たことで申請を取りやめることになったり、逆にスムーズに進んだという事例も報告されています。
最初の相談で不安や疑問を解消することで、その後の手続きも安心して進められます。
2. 申請書類の作成と提出
事前相談で方向性が決まったら、必要な申請書類を作成し、法務局に提出します。
先ほども書いたように、申請書類には「戸籍謄本や住民票」「相続関係がわかる除籍謄本」「遺産分割協議書」「登記事項証明書」「不動産の公図や地積測量図」「固定資産税評価証明書」「現地写真」など多数の資料が必要です。
しかも、書類の一部に不備があれば、手続きが大幅に遅れたり再提出が求められることもあり、かなり面倒なやり取りとなります。
また、共有名義の土地では「全員の同意書や追加書類も必要になるため、事前にしっかり準備しましょう。
正確で漏れのない書類作成が、スムーズな申請とその後の審査につながります。
関連記事

3. 審査・現地調査・承認
申請書類が受理されると、法務局による審査と現地調査が行われます。
この過程では「土地の現況」や「権利関係」、「管理負担の有無」などを詳細にチェックされます。
たとえば、隣地との境界が曖昧だったり、現地に不法投棄や工作物が発見された場合、承認されないケースも少なくありません。
また、過去の利用状況や周辺環境によっても審査結果が左右されることがあります。
この段階で問題がなければ、国への帰属が正式に認められます。
4. 負担金の納付と土地の引き渡し
審査に通過し、承認が下りたら負担金(原則として20万円)を納付します。
負担金の支払いが完了すると、正式に土地が国に引き渡され、所有者としての義務もすべて解消されます。
具体的には、「固定資産税」や「管理の義務」から解放されるほか、将来的なトラブルのリスクもなくなるというわけです。
制度の各段階をしっかり理解し、一つひとつ確実に進めることが成功のポイントです。
\相続した「いらない土地」を高額買取/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット

相続土地国庫帰属制度には、所有者にとってメリットがある一方で、注意すべき「大きなデメリット」も存在します。

ここでは、主な利点とリスクの両面について具体的に解説します。
メリット|固定資産税・管理負担から解放
「相続土地国庫帰属制度」の最大のメリットは、不要な土地の固定資産税や管理負担から解放されることです。
国に土地を引き渡すことで、以後の所有者としての責任がすべてなくなるからです。
たとえば、毎年発生する「固定資産税」の支払いが不要になり、草刈りや清掃などの維持管理の手間も解消されます。
さらに、遠方の土地や活用できない山林・農地など、自分ではどうすることもできなかった資産をすっきり手放せるのも大きなメリットです。
この制度を利用することで、将来の相続人に負担を残す心配もなくなり、「負動産」を巡る家族間のトラブル予防にも役立ちます。
デメリット|条件が厳しい・費用が高い・手間と時間
一方で、「相続土地国庫帰属制度」には、見逃せないデメリットもあります。
最大のデメリットは、利用できる土地の条件が厳しく、誰でも簡単に利用できるわけではない点です。
たとえば、建物や工作物が残っていたり、権利関係が複雑な土地、汚染や境界問題がある土地は申請時点で却下されます。
また、審査手数料や負担金が高額なことも多く、1筆ごとに数万円から20万円以上の出費が必要です。
さらに、申請から承認・引き渡しまでに1年以上かかるケースもあり、書類準備や現地調査など手続きにかなりの手間と時間を要します。
「相続土地国庫帰属制度」は物件を手放せるメリットはあっても、これだけのお金と時間と手間をかける必要があるということです。
その点、専門の買取業者に売却すれば、一切費用をかけないどころか、まとまった現金を手に入れつつ「いらない土地」のリスクから解放されるのです。
査定も「完全無料」なので、まずは気軽に相談してみるといいですよ。
\相続した「いらない土地」を高額買取/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
いらない土地を持ち続けるリスクとは?

価値の低い土地を持ち続けるリスクと、これからの制度変更による影響を整理します。
税金や管理負担、さらには登記義務や民法改正など、土地所有者が知っておくべき重要なポイントを解説します。
所有し続けるデメリット(税金・管理・損害賠償)
いらない土地を所有し続けると、多額の「固定資産税」や「維持管理費」がずっと発生し続けます。
草刈りや除草、境界管理など負担が増え、特に遠隔地なら現地に行く時間や費用もバカになりません。
加えて、無人地帯になっている土地で近隣に損害を与えた場合、所有者責任を問われ「損害賠償」を支払うリスクもあります。
つまり、使わなくても手間や費用、リスクが蓄積し、知らず知らず家計や精神的ゆとりを圧迫する可能性が高いのです。
不動産登記の義務化・民法改正のポイント
今後、不動産登記制度は「義務化」が強化され、相続登記や所有者申告が必要になります。
これは、所有者情報を明確にして登記簿の信頼性を高める狙いがあります。
2024年施行の民法改正では、相続登記が義務化され、未登記の土地を放置すると罰則や過料が科される可能性もあります。
また、「所有者申告登記制度」も設けられ、土地が放置されがちな地域では自治体への報告義務が増えています。
こうした法改正により、いらない土地をそのままにすることは、税金リスクだけでなく法的リスクにもつながるため、早めに対応を検討する必要があります。
\相続した「いらない土地」を高額買取/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
いらない土地を国に返したい人が今すぐできること

いらない土地を国に返したい、または手放したいと考えたとき、どんな行動を取ればいいのでしょうか。
制度や法律が複雑なため、一人で悩まず早めに信頼できる専門家や業者へ相談することをおすすめします。

最後に、すぐに実践できる2つの具体的なアクションについて解説します。
専門家(司法書士・弁護士)に相談するメリット
いらない土地の問題をスムーズに解決するために、司法書士や弁護士など不動産に強い専門家に相談するのは一つの方法です。
相続や登記、法的な条件、各種申請書類の作成など、個人では対応が難しい点をサポートしてもらえるからです。
たとえば、土地の権利関係を正確に調査してもらう、国庫帰属制度の対象可否を判断してもらう、複雑な相続や共有持分の整理を依頼することができます。
トラブルや法改正への対応、税金・費用のシミュレーションも専門家なら的確にアドバイス可能です。
ただし、司法書士や弁護士は物件の「売却」に対するサポートはしてくれませんので、それについては理解しておく必要があります。
一番のおすすめは「専門の買取業者」に相談すること!
結論的に一番おすすめなのが、訳あり物件の「専門買取業者」に売却することです。
この方法の一番の魅力は、手続きがカンタンでスピーディーに現金化できる点にあります。
たとえば、国や自治体に返せない土地や、買い手が見つかりにくい土地でも、専門業者なら柔軟に対応してくれます。
専門の買取業者は、物件の再生ノウハウや独自の売却ルートを持っているため、多くの方にとって「いらない土地」でも高値で買い取ってくれるのです。
しかも、仲介で売却する場合に付きまとってくる「契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)」も免責されるため、売れた後の心配も一切ありません。
自分だけで悩まず専門家や業者を活用すれば、損することなく「いらない土地」の問題を解決することができるのです。
査定は「完全無料」ですし、しつこい営業電話なども一切ないので、あなたが「いらない土地」を処分したいと考えているのなら、気軽に相談してみるといいですよ!
\相続した「いらない土地」を高額買取/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
いらない土地の手放し方|まとめと次に取るべき行動

いらない土地を相続した場合、国に返す「相続土地国庫帰属制度」は一つの選択肢ですが、要件のハードルが高くすべての土地が対象になるわけではありません。
いざ申請が通っても、数十万円単位のお金を払って物件を手放す状態ことは大きなデメリットです。
その点、専門の買取業者なら、カンタンかつスピーディーに現金を受け取りながら、物件を手放すことが可能です。
土地を放置していると、税金や管理リスク、法改正による義務も増え、トラブルや損失につながります。
固定資産税や管理リスクから自由になるためにも、早い段階で「専門の買取業者」に相談することをおすすめします。
査定は完全無料ですので、まずは気軽に「無料査定」から試してみるといいですよ。
\相続した「いらない土地」を高額買取/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
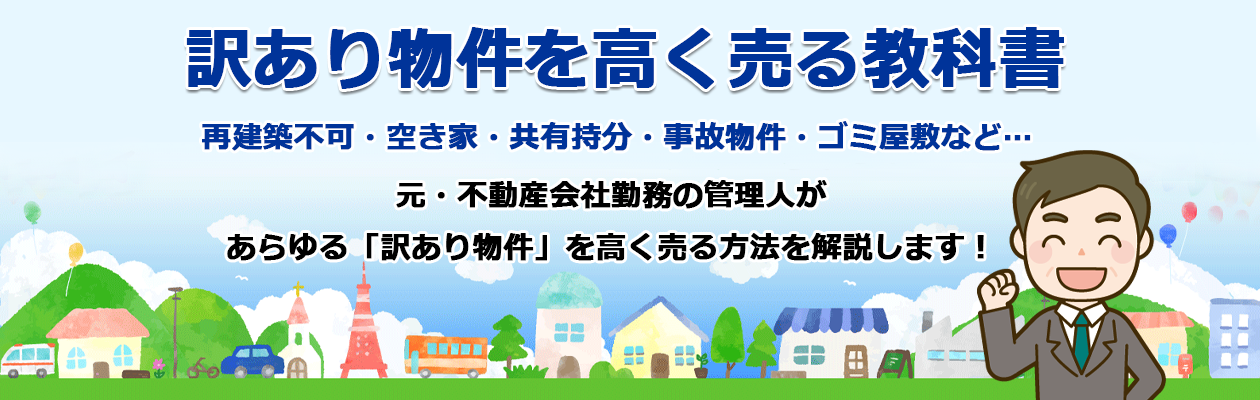



コメント