この記事では、管理不全空き家の基準や、特定空家との違いなどについて詳しく説明していきます。
「うちの空き家・・・もしかして管理不全空き家に該当するのでは?」
今現在、空き家を所有している人なら、そんな不安を持っているかもしれません。
「管理不全空き家」は、2023年の法改正で新たに設けられた区分です。

知らないまま放置すると、固定資産税の増額や行政からの指導、最悪の場合は「強制解体」も現実のリスクとなってしまいますので、ぜひ最後までお読みください。
\売れない空き家も高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
管理不全空き家とは?法改正のポイントと基礎知識

「管理不全空き家」は、2023年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」によって新設されました。

ではまず、初心者の方にもわかりやすく管理不全空き家の基準や、特定空き家との違いなどについて解説します。
管理不全空き家の基準と定義について
「管理不全空き家」とは、文字通り、適切に管理されていないことで周囲の生活環境や安全に悪影響を及ぼす恐れがある空き家を指します。
これまで「空き家対策」として主に問題視されてきたのは、倒壊や火災の危険がある「特定空き家」のみとなっていました。
しかし、現実にはそこまで危険ではなくても、放置すれば将来的に深刻な問題を引き起こす空き家が増加しています。
こうした背景から、社会全体で空き家管理の必要性が高まり、「管理不全空き家」という段階が新たに設けられたのです。
これは所有者に対して、早めの対策を促す狙いがあり、近隣トラブルや地域の環境悪化を未然に防ぐことが目的となっています。

つまり、現時点では「特定空き家」とまでは行かなくても、「管理不全空き家」という名前のリーチがかかったみたいなものね。
2023年の法改正で変わった点は?
2023年12月に施行された空家法改正では、「管理不全空き家」の新設が最大のトピックとなりました。
これにより、従来の「特定空き家」だけでなく、その一歩手前の状態の空き家も行政の指導対象となったのです。
従来は、「建物の倒壊」や「著しい衛生悪化」といった緊急性が高い場合のみ、行政から厳しく指導・勧告の対象とされていました。
しかし今後は、軽度でも「管理不全」が認められると、より早い段階で改善指導が行われます。
この法改正は、空き家問題の深刻化を防ぐとともに、所有者が自発的に管理・活用を考えるきっかけを与えるものと言えるでしょう。
関連記事

「特定空き家」との違いは?

「特定空き家」と「管理不全空き家」は似ているようで、行政の対応や認定の基準が異なります。
表にすると以下のようになります。
| 特定空き家 | すでに倒壊の恐れや著しい衛生被害、景観の著しい悪化など、明らかな危険が生じている状態 |
| 管理不全空き家 | まだ重大な被害が起きてはいないものの、雑草やごみの放置、軽度の外壁破損、長期不在による不衛生など、将来的な問題が懸念される段階 |
行政による指導も、「特定空き家」は命令や強制執行まで及ぶ場合がありますが、「管理不全空き家」は、まず所有者への改善勧告や指導が中心となります。
このように、両者はリスクの大きさと行政の介入の強さで区分されています。
ただし、管理不全空き家にも、見逃すことのできない大きなデメリットが存在しますので、次で解説します。
\売れない空き家も高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
管理不全空き家に認定されるとどうなる?固定資産税やデメリット

管理不全空き家に認定されると、単なる指導だけでなく、金銭面・生活面での負担やリスクも大きくなります。

ここでは、特に注目されるデメリットや問題について詳しく解説します。
住宅用地特例の適用除外と税負担の増加
管理不全空き家に認定されてしまうと、最も大きなデメリットの一つが「住宅用地特例の適用除外」です。
通常、住宅が建っている土地は「固定資産税」や「都市計画税」が大幅に軽減される「住宅用地特例特例」があります。
ところが、「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されると、この特例が外され税額が大きく跳ね上がってしまいます。
たとえば「固定資産税」なら、これまでの最大6倍にまで増額されることもあり、所有者の経済的負担は急激に重くなります。
管理不全空き家の認定は、「特定空き家の前段階」というだけではなく、すでに家計へのダメージに繋がっているのです。
\売れない空き家も高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
行政からの指導・勧告の流れ
管理不全空き家に認定されると、行政からはまず改善を促す「指導」や「勧告」が行われます。
具体的には、空き家の管理状況を確認した自治体職員が、所有者に対して改善を求める通知を出し、期限内に対応がなければ、より厳しい措置へと移行します。
それでも対応しない場合は、「特定空き家」へ格上げされ、最終的には命令や強制執行(行政代執行)もあり得ます。
このように、行政の介入は段階を追って強まるため、認定後は迅速に対応することが重要です。
関連記事

近隣トラブルや安全面のリスク
管理不全空き家が放置されることで、近隣住民など周囲への影響やリスクも拡大します。
たとえば、草木の繁茂による害虫発生、不法投棄、空き家への不審者侵入や火災リスクなど、近隣住民とのトラブルにつながりやすくなります。
また、建物の劣化が進行すれば、倒壊や部材の落下など、思わぬ事故につながる可能性も高まります。
こうしたリスクは所有者自身の責任になるだけでなく、地域全体の安全やイメージにも悪影響を与えてしまうため、近隣住民との人間関係トラブルに発展しやすいのです。
\売れない空き家も高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
管理不全空き家の認定基準と主なチェックポイント

管理不全空き家かどうかは、単に空き家であるというだけでは決まりません。
実際には、建物や敷地の状態・管理状況など複数のポイントがチェックされ、問題が認められた場合に「管理不全」と判断されます。

ここでは、具体的な基準や、どのような場合に注意が必要なのかを詳しく解説します。
どんな状態が「管理不全」とされるのか
管理不全空き家と判断される主なポイントは、「建物や敷地が適切に管理されていないかどうか」です。
たとえば、屋根や外壁が壊れて雨漏りしている、雑草や樹木が生い茂っている、ゴミや不法投棄物が放置されている・・・こういった状態が該当します。
また、防犯上の問題(窓やドアの施錠忘れ、不審者の侵入しやすさ)、衛生上の問題(悪臭や害虫の発生)も管理不全とみなされやすいです。

つまり「周囲に迷惑をかける可能性があるか」「将来的に危険や衛生問題につながるか」が判断の目安になるってことなのね。
管理不全空き家の具体例

具体的には、次のような空き家が「管理不全」にあたります。
・敷地内に大量のゴミや不要物が積み上げられている
・建物の外壁や屋根が劣化・破損しているが修繕されていない
・窓や玄関が壊れ、簡単に侵入できる状態になっている
・悪臭や害虫・ネズミなどが発生し、周辺住民から苦情が出ている
こうした状態は、軽度でも早めに対処しないと、より大きな問題へ発展する可能性が高いです。
関連記事

特定空き家へ移行するリスクとは
管理不全空き家を放置していると、やがて「特定空き家」へと認定が進むリスクがあります。
特定空き家は、すでに倒壊や火災など深刻な危険や、周辺への著しい悪影響が認められる段階であり、行政による命令や強制的な解体も現実味を帯びてきます。
管理不全の段階で改善しなければ、税負担増加・資産価値の低下・近隣とのトラブル・強制解体といった重大なデメリットにつながります。
そのため、管理不全と判断された時点で、できるだけ早く具体的な対応を取ることが、リスク回避のために非常に重要です。
\売れない空き家も高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
管理不全or特定空き家にならないための「4つの対策」とは?

空き家を放置してしまうと、管理不全や特定空き家に指定され、税負担や近隣トラブルのリスクが高まります。

最悪の事態を免れるためにも、ここでは、主な4つの対策について解説します。
1. 自分で住む
空き家を自分で住まいとして利用するのは、最もカンタンですぐにできる対策と言えるでしょう。
居住すれば、日々の管理や修繕も行き届き、建物の傷みや防犯面でのリスクも大幅に減少しますからね。
ただし、仕事などの都合ですぐに引っ越せない場合や、リフォーム費用が大きくかかる場合もあるため、慎重な判断が必要です。
また、古い建物では耐震性や断熱性が不十分なケースもあり、思ったより住み心地が悪かったり、安心して住めないケースも少なくありません。
実際に住む際は、建物調査や必要なリフォーム計画を事前に検討しておくことが大切です。
関連記事

2. 賃貸物件にする
空き家を賃貸物件として貸し出すことで、第三者の利用を通じて日常的な管理が行き届き、老朽化やトラブルの予防につながります。
この方法の場合、賃料収入も得られるため、家計へのメリットも期待できます。
ただし、賃貸化するためには、初期のリフォーム費用がかかりますし、入居者募集、契約・管理の手間やコストも発生します。
また、築年数が古い場合は、入居希望者がなかなか見つからないリスクもあります。
この方法はれっきとしたビジネスであるため、賃貸経営が初めての方は、専門家に相談しながら費用対効果や賃貸需要をよく調査した上で始めましょう。
\売れない空き家も高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
3. 解体・更地にして駐車場等で活用する
建物の管理や活用が難しい場合は、解体して更地にし、駐車場や家庭菜園、資材置き場など土地活用をするという方法もあります。
解体すれば倒壊や火災のリスクがなくなり、近隣迷惑や管理の手間も軽減されます。
ただし、解体費用は一般的に、木造30坪の家で120万円~180万円程度、鉄骨造で150万円~330万円程度、RC造で180万円~360万円程度が目安とされていますので、かなりな出費を覚悟しなければなりません。
また、更地にすると固定資産税の軽減特例がなくなり、税負担が大幅に増えるというデメリットもあります。
土地活用で収益が見込めない場合は、かえって負担が重くなる場合もあるため、全体の収支や将来の計画をよく考えて決断しましょう。
4. 売却する

空き家を今後使う予定がない場合は、売却によって早めに手放すことがもっともおすすめの対策です。
ちなみに、相続した空き家の場合、一定期間内の売却で、3,000万円の特別控除が適用される場合があります。
ただし、古い空き家や老朽化した建物の場合、一般の不動産仲介では買い手がなかなか見つからず、売却に数年を要したり、値下げを繰り返してしまうリスクがあります。
そのため、空き家の状態が悪い場合は「訳あり物件専門」の買取業者に直接売却する方法がもっともおすすめです。
専門の買取業者なら、古家付き土地や老朽化した物件でも現状のまま買い取ってくれます。
リフォームや清掃、修繕の費用などが不要ですし、ほとんど丸投げで大丈夫なので面倒な手間も一切かかりません。
また、直接買取のため仲介手数料が発生することなく、スピーディーな現金化が可能です。
仲介で売却した場合に心配な「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」も免責にできるため、スッキリと手放すことができるのです。
査定は「完全無料」なので、所有している空き家が売却できるかどうか不安な方は、気軽に相談するといいですよ。
査定額は「売却するか・しないか」の判断材料にもなりますからね~
\売れない空き家も高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
まとめ|管理不全空き家はリスク大!放置せず早めの対策を

管理不全空き家や特定空き家に認定されると、税金の増額や近隣トラブル、最悪の場合は行政による強制措置など、大きなデメリットを抱えることになります。
2023年の法改正によって、以前よりも早い段階で行政の指導や勧告が入るようになったため、空き家は「使わないなら放置せず、具体的な対策を取る」ことが大切です。
自分で住む・貸す・解体・売却といった選択肢がありますが、特に使う予定がなければ、専門の買取業者への売却がもっとも現実的で安心できる解決策です。
空き家問題を先送りせず、今すぐ行動に移すことが、将来のリスク回避と大切な資産の守りにつながります。
空き家の問題は、「そのまま」にせず、今日から一歩踏み出しましょう!
\売れない空き家も高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
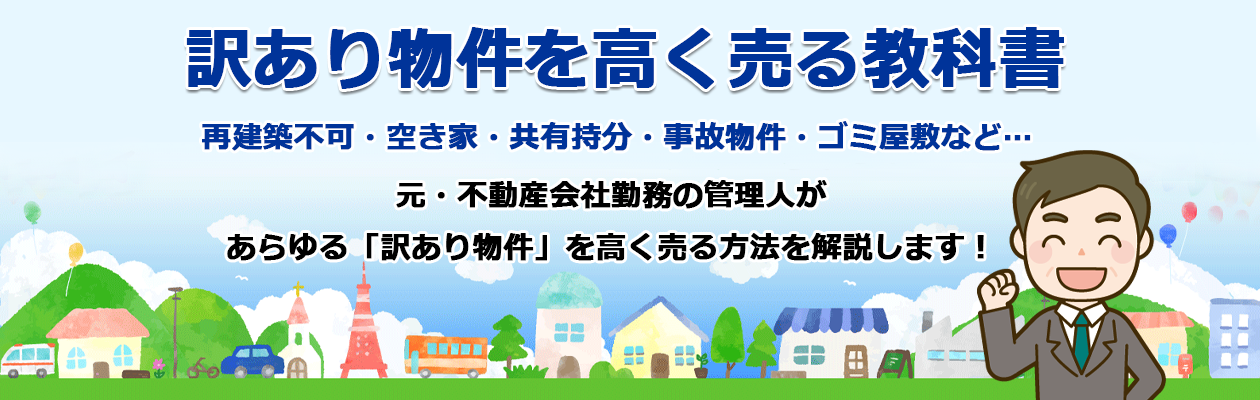



コメント