
孤独死が起きた家を相続・所有すると、「孤独死の物件に告知義務はあるのか?」と不安に思う方が多いでしょう。
2021年に国土交通省が「告知義務に関するガイドライン」を示したことで、自然死や孤独死でも告知の必要・不要の線引きが明確になりました。
今回は、孤独死があった物件が事故物件に該当するケース、告知義務の範囲、さらに売却や活用の方法について詳しく解説します。
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
「孤独死と告知義務の基本」とは?

孤独死があった家を売却や賃貸に出す際、多くの人が気になるのが「告知義務があるのかどうか」でしょう。
結論から言えば、これはケースバイケースで状況によって違います。

それではまず、事故物件の定義から説明し、それが分かった上で孤独死が事故物件になるケース・ならないケースについて解説します。
そもそも事故物件の定義とは?
事故物件とは、過去に自殺や殺人、火災などによる死亡事故が起き、その事実が買主や借主に心理的な抵抗を与えると判断される物件のことです。
この定義は、単に「建物で人が亡くなった」という事実だけではなく、取引相手が物件の価値を低く見積もったり、住むことに不安を感じたりするかどうかが基準になります。
たとえば、病死であっても、発見が大幅に遅れて強い異臭や汚損が残った場合(特殊清掃が必要なケースなど)には、事故物件として扱われることがあります。

つまり、事故物件かどうかは死因や状況によって判断されるってことね。

さらに言えば、その死因や状況を購入希望者がどう感じるのかという「心理的影響」が大きなポイントとなるのです。
孤独死は必ず事故物件になるわけではない
孤独死が起きたからといって、必ずしも事故物件と認定されるわけではありません。
たとえば、病気や老衰による自然死ですぐに発見された場合には、心理的瑕疵と見なされず告知義務が生じないケースが多いのです。
一方で、発見が遅れて室内が汚損したり、特殊清掃が必要になった場合は、心理的にも物理的にも影響が大きいため、事故物件として扱われる可能性が高まります。
孤独死は、高齢化社会の中で増えている現象ですが、そのすべてが「告知が必要な事故物件」に該当するわけではありません。
実際には、発見までの経緯や遺体の状況によって扱いが変わるため、判断には注意が必要です。
関連記事

心理的瑕疵・物理的瑕疵と告知義務の関係

孤独死が発生した物件に告知義務があるかどうかは、「心理的瑕疵(しんりてきかし)」や「物理的瑕疵(ぶつりてきかし)」に該当するかで決まります。

瑕疵(かし)ってなに?
心理的瑕疵とは、過去の出来事が理由で入居希望者が不安を感じる要因のことです。
自殺や殺人だけでなく、長期間発見されなかった孤独死もこれに当たる場合があります。
一方、物理的瑕疵は建物自体に残ったダメージを指し、異臭やシミなど清掃やリフォームが必要な状態が典型例です。
こうした場合は、買主や借主にきちんと告知しなければトラブルにつながります。
つまり、孤独死に伴う告知義務は「死亡そのもの」ではなく、その影響が心理面や建物の状態に及ぶかどうかで判断されるのです。
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
国土交通省のガイドラインによる告知義務の範囲

孤独死や自然死があった場合、告知義務が発生するかどうかの判断には、国土交通省が示したガイドラインが大きな基準となります。
2021年10月に策定されたこの指針は、これまで曖昧だった事故物件の扱いを整理し、売主や貸主がどのように対応すべきかを明確にしました。

それでは、告知義務にかかわる代表的な3つのケースについて説明します。
1. 自然死・孤独死が告知義務の対象になるケース
ガイドラインによれば、通常の老衰や病気による自然死で、かつ早期に発見された場合は原則として告知義務は発生しません。
たとえば、一人暮らしの高齢者が自宅で孤独死したけど、たまたま訪問した家族がすぐに見つけることができたのであれば、告知義務はないということになります。

つまり「孤独死が起きたから事故物件になった!」と、すぐに判断するべきではないということね。
「亡くなった事実そのもの」ではなく、発見までの状況や物件への影響が重要な判断基準とされているわけですね。
2. 発見が遅れた孤独死と特殊清掃が必要なケース

孤独死の中でも特に注意が必要なのは、発見までに時間がかかり住環境に深刻な影響が出てしまったケースです。
たとえば、遺体から発生した体液や臭気が床や壁に染み込み、通常の清掃では対応できず「特殊清掃」を依頼しなければならない場合があります。
こうした事態は、入居希望者に強い抵抗感を与えるため、心理的瑕疵とされて告知義務の対象となります。
孤独死がすべて事故物件になるわけではありませんが、発見の遅れと清掃の有無は大きな分かれ目になるのです。
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
3. 自殺・他殺など事件性がある場合の告知義務

ガイドラインでは、自殺や他殺といった事件性の高い死亡については明確に告知が必要とされています。
これらは、社会的にも強いインパクトを持ち、心理的瑕疵が大きいと判断されるからです。
たとえば、自殺があった賃貸物件では概ね3年間は必ず告知が必要とされます。
売買の場合は、さらに購入者の判断に大きな影響を与えるため、常に告知義務が生じることになります。
孤独死よりもさらに厳しい基準で告知が求められる点を押さえておくことが大切です。
関連記事

売買と賃貸で異なる告知義務の基準
ガイドラインは、売買と賃貸で告知義務の範囲を分けています。
先ほども書きましたが、賃貸ではおおむね3年を経過すれば心理的瑕疵の影響が薄れるとされ、原則として告知義務は不要になります。
ただし、入居者が変わっても3年の縛りは消えないというポイントには注意が必要です。
一方で、売買取引の場合は、人が亡くなってから何年過ぎようとも告知義務がなくなることはありません。
買主が将来的に長く住むことを前提とするため、心理的瑕疵の影響は賃貸より重視されるからです。
この違いを理解しておかないと、契約不適合責任やトラブルに発展する恐れがありますので、くれぐれも注意してください。
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
告知義務を怠った場合のリスク

孤独死が発生した物件を売却や賃貸に出す際、告知義務を怠ると重大なトラブルにつながります。
不動産取引は信頼関係のうえに成り立っているため、買主や借主が「重要な事実を知らされなかった」と感じれば、契約の取り消しや損害賠償請求につながる可能性があります。

では、具体的にどのようなリスクがあるのかを整理しておきましょう。
契約不適合責任を問われる可能性がある
孤独死の事実を告知せずに取引を進めると、後から発覚した際に「契約不適合責任」を追及される恐れがあります。
契約不適合責任とは、売主が買主に伝えるべき重要な情報を隠していた場合(漏れていた場合も含む)などに負わなければならない責任のことです。
たとえば、孤独死が発生して発見が遅れ、「特殊清掃」をしたのにも関わらず履歴を隠して売却したとします。
その場合、買主が「心理的瑕疵がある」と感じて訴えれば、「契約解除」や「損害賠償」を請求される可能性があります。

告知義務を怠ると、売却益以上の「金銭的負担」や「信用の失墜」につながる恐れがあるのね。
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
判例からみる告知義務違反の事例

過去の裁判例では、告知義務を怠った売主が責任を負ったケースがいくつも存在します。
たとえば、孤独死で遺体の発見が遅れ、室内に汚損が残ったにもかかわらず、その事実を隠して売却したところ、心理的瑕疵と認定され契約が取り消された事例などは典型例です。
一方で、自然死で発見が早く物件に影響がなかった場合には「告知不要」と判断された判例もあります。
このように、告知義務違反の判断はケースごとに異なるため、所有者は慎重な対応が求められるのです。
関連記事

トラブルを防ぐために所有者が注意すべき点
告知義務違反によるトラブルを避けるためには、所有者が正確な情報を把握し、適切に開示することが不可欠です。
孤独死が発生した際には、発見の状況や特殊清掃の有無などを整理し、不動産会社や専門家に相談することが望まれます。
また、判断に迷う場合は「とりあえず開示しておく」ことがリスク回避につながります。
不安要素を隠すより、あらかじめ説明して信頼関係を築いた方が、結果的に取引はスムーズに進みます。
告知義務は、所有者にとっては大きな負担に感じるかもしれませんが、将来的なトラブルを避けるための重要な手段だと理解しておくべきです。
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
孤独死があった家の売却・活用方法

孤独死が発生した家を所有すると、「売れるのか」「借り手は見つかるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。
しかし、事故物件として扱われる場合でも、適切な方法を選べば活用や売却は可能です。

では、孤独死が起きた物件で「事故物件に該当しない場合・該当する場合」の、大きく2つに分けて売却・活用方法について説明します。
事故物件に該当しない場合の売却方法
まずは、孤独死であっても、事件性のない自然死や老衰で早期に発見された場合は、事故物件に該当しないケースが多いです。
その場合、心理的瑕疵の影響が少なく、通常の不動産と同じように市場で売却できる可能性があります。
通常物件と同じく「相場価格」での売却が期待できるため、一般の仲介業者を通じて買主を探す方法が良いでしょう。
ただし、買主から死亡についての質問があった場合には答える義務が生じますので、その点には注意が必要です。
そのような場面に備えて状況を説明できるよう、発見時の詳細などを整理しておくと安心です。
関連記事

事故物件に該当する場合の売却方法
発見が遅れて「特殊清掃」を行ったケースや、心理的に抵抗を与える事情がある場合は事故物件として扱われます。
この場合は、通常の仲介で買主を見つけるハードルが一気に上がるため売却が難しく、期間が長引いたり、価格が相場より大幅に下がる傾向があります。
そのため、仲介で時間をかけて買主を探すか、専門の買取業者へ直接依頼するかを選ぶ必要があります。
特に、早期に売却したい場合は、買取業者に相談する方が現実的な選択肢となります。
仲介ではなく買取を選ぶメリット

事故物件として扱われる家は、仲介よりも買取を選ぶメリットの方が圧倒的に大きいです。
なぜなら、買取の場合は「不動産会社」が直接購入するため、売却までのスピードが早く、最速で即日の現金化も可能だからです。
また、仲介で必要となる「内覧対応」や」長期間の売却活動」が不要なため、近所にバレたり変な噂を立てられる可能性が低く、精神的な負担を減らせるのも利点です。
通常物件としての相場よりは価格は下がりやすいものの、確実に売却できる安心感を優先するなら買取が断然おすすめです。
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
事故物件の売却は「買取」がおすすめ!5つの理由とは?

「事故物件」を高く売却するためには「専門の買取業者」がおすすめです。
その理由は、大きく分けると以下の5つです。
1、事故物件の専門家だから「高値買取」が可能
2、仲介手数料(物件価格の3%+6万円+税)がかからない
3、現金化がスピーディー
4、契約不適合責任を負わなくて良い
5、近隣に知られずに売却できる
1、事故物件の専門家だから「高値買取」が可能

専門の買取業者は、文字通り事故物件のような「訳あり物件の専門家」です。
「訳あり」の不動産に特化した独自販売ルートがあることはもちろん、物件に応じた再生ノウハウも持っており、スムーズな買取が可能になります。
一見「無価値」に見える訳あり物件でも、あらゆる再生ノウハウを駆使して有効活用することができるため、物件の本当の価値を見抜いて買い取ってくれるのです。
また、仲介の不動産会社で断られたり、値段が付かなかった物件でも、訳あり物件専門の買取業者なら問題ありません。
相談する業者にノウハウがない場合、訳あり物件は最初から「売れない」と決めつけているため、断られるケースが多いです。
しかし、専門の買取業者は、再建築不可、空き家、ゴミ屋敷、事故物件、共有持分、どんな物件でも査定してもらえます。
他社で断られたからと言って諦めなくても大丈夫です。
2、仲介手数料(物件価格の3%+6万円+税)がかからない

専門の買取業者は、不動産会社が直接買い取ってくれるサービスなので、仲介手数料がかかりません。
仲介手数料は、「物件価格の3%+6万円+税」が一般的です。
仮に物件価格が1000万円だった場合・・・
仲介なら、およそ40万円ほどの手数料を取られてしまうということ。
専門の買取業者なら、仲介手数料は一切かからないため、その分さらに上乗せした金額提示をすることが可能になるのです。
3、現金化がスピーディー

不動産会社が直接買い取ってくれる「専門の買取業者」は、現金化がとてもスピーディーです。
なぜなら、わざわざ買いたい人を探す手間や時間が必要なく、目の前の不動産会社がすぐに買い取ってくれるからです。
仲介の不動産会社に依頼すると、【相談】→【査定】→【販売価格の決定】→【販売活動】という流れを踏む必要があるため、まずは着手するまでにかなりな時間を要します。
実際に販売活動がスタートしても、何人もの見込み客に物件を見てもらうのが一般的。
しかも、やっとのことで契約までこぎ着けたとしても、事故物件はローン審査が通りづらいため、それですべてがボツになることも、ザラにあります。
専門の買取業者なら【相談】→【査定】→【契約】と3ステップで完了。
しかも、資金が豊富な不動産会社が買い取ってくれるため、ローンを通す必要もなく、すぐに現金化できるのです。
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
4、契約不適合責任を負わなくて良い

契約不適合責任ってなに?

契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは、カンタンに言うと不動産売買の際に「契約書した内容と物件の数量や品質が一致していない時に、売主が負うべき責任」のことです。
つまり、引き渡した物件が契約書に書かれた内容と違っている(契約不適合)場合、買った人が困るため、売主は責任を負う義務があるわけです。
例えば、雨漏りやシロアリが発生している物件なのにもかかわらず、それが後で発覚して契約書に書かれていなければ、売主は責任を負わなければなりません。
また、事故物件であることを告知せずに販売した場合にも、契約不適合責任は適用されます。
なお、仲介で売却した物件に不具合があった場合は、以下のような「契約不適合責任」を負わされる可能性があります。
・不具合箇所の修理
・売却金額の減額
・損害賠償請求
その点、訳あり物件の買取専門業者は会社が直接買い取ってくれるため、このような請求がされることは一切なく、すべての「契約不適合責任」が回避されます。
5、近隣に知られずに売却できる

事故物件の売却をご近所に知られたくない売主さんは、とても多いです。
- 「事故物件であることを知られたくない」
- 「近所で変な噂を立てられたくない」
- 「これ以上マイナスな要因を作りたくない」
など、いろいろなご心配をされるわけですね。
仲介の場合、買主を探すためにインターネット広告やチラシなどを使いますし、物件を見たい人の出入りもあるため目立つことが多く、近隣にバレやすいと言えます。
しかし、買取の場合は、直接「会社」が物件を査定し、そのまま買い取るため、そもそも買いたい人を探す必要がありません。
もちろん、広告で人目に晒されることもありませんし、不特定多数の人の出入りもないです。
売買のスピードも速いため、ほとんど近隣住民に気づかれず、こっそり売却することが可能となります。
査定は「完全無料」ですし、入力も1分で終わるので、まずは気軽に「無料査定」を試してみるといいですよ!
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
まとめ:孤独死の告知義務を正しく理解し、リスクを避けて売却する

孤独死があった家は、発見状況や物件への影響によって告知義務の有無が変わります。
早期発見で、特殊清掃が不要な場合は告知不要なこともあります。
ですが、発見が遅れて心理的・物理的瑕疵が残った場合は事故物件扱いとなります。
その場合、告知義務を怠ると契約不適合責任を問われるリスクがありますのでご注意。
売却を検討する際は、ガイドラインを正しく理解し、状況にあった方法を選択することが大切です。
事故物件に該当しない場合は、通常の仲介不動産会社に依頼するといいでしょう。
該当する場合は、通常の売却ではかなり厳しいので、専門の買取業者への依頼がおすすめです。
まずは、売却するしないの判断にもなりますので、気軽に無料査定を依頼してみましょう。
\事故物件でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
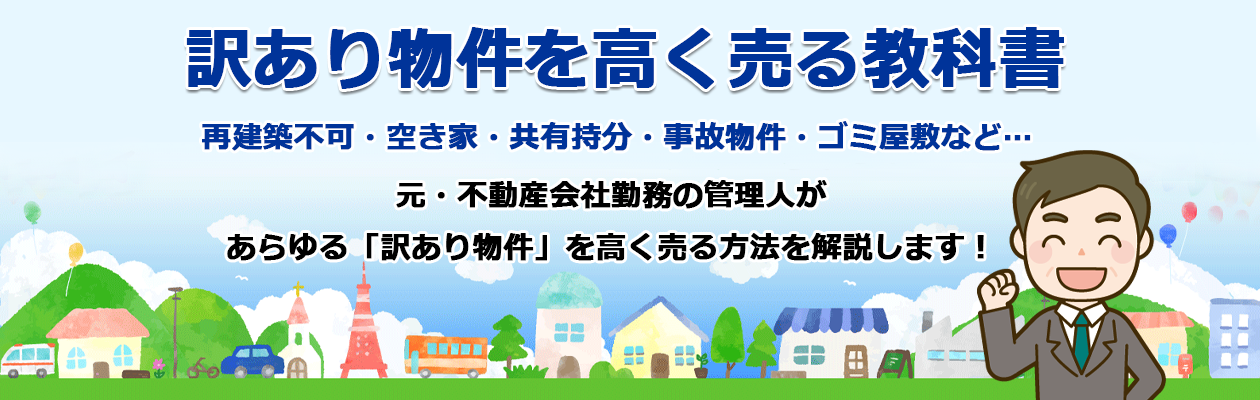



コメント