
再建築不可物件を所有している人の中には、以下のような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。
「私の再建築不可物件、これから一体どうなるの?」
- 建て替え出来ない
- しかし売るのも難しい
- 2025年に法律が厳しくなって更にヤバいかも?
などなど・・・
今回は、再建築不可物件がこれからどうなっていくのかについて、また持ち続けることの7つのリスクについてご説明します。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、ほとんどの場合、建築基準法における「接道義務」を満たしていないため、新たに建物を建てることができない(再建築不可)の土地のことです。
接道義務とは、建築基準法上の道路(幅4m以上)に土地が2m以上接していなければならないというルールのこと。
このルールが守られていない土地は、「建築基準法違反」になるため、建物を建てるための「建築確認申請」が通りません。
そのため、現状の建物を壊して新たに建て替える「再建築」が出来ないのはもちろん、大規模な増築や改築もすることが出来ないのです。
再建築不可物件はこれからどうなる?2025年の法改正について


再建築不可物件を取り巻く環境は、年を追うごとに厳しくなっています。
では、どんな点が厳しいのでしょうか?
まずは、建物の老朽化です。
そもそも再建築不可物件とは、1950年の建築基準法、または1968年に都市計画法が制定されたことで、出来上がった物件です。
それまでは普通に建築できていたものが、法改正によって建築できなくなったわけですね。
2024年の時点で、ザッと計算しても56年間以上は経過しているため、老朽化や損傷が激しい建物がほとんどです。

しかも、建て替えができないため、更地にも出来ない・・・となれば、古い建物を修繕しながら使うしかないため、日を追うごとに状況は厳しくなる一方ね。
さらにそこへ来て、2025年4月には建築基準法の改正が決定しており、より一層厳しい現状が将来待ち受けています。
詳しくは後ほど説明しますが、今まで建築確認申請が不要だった「4号特例」が縮小される予定です。
4号特例とは、都市計画地域など以外で「延べ床面積500㎡以下で、2階建て以下の建物なら建築確認申請が免除される」という特例制度のこと。
2025年3月までは、この特例が適用されます。
そのため、2階建ての一軒家で延べ床面積500㎡以下なら、建築確認申請なしでリフォームすることが可能です。
ところが、2025年4月の改正後は、この条件が縮小されるため、一般的な一戸建ての大規模リフォームが事実上困難になってしまうのです。
再建築不可物件の中には、建物さえリフォームできれば何とか活用できるという物件は、まだまだあります。
しかし、この法改正によって、一気に活用できる範囲が狭くなったと言えるでしょう。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
再建築不可物件を持ち続けるリスク7選


では、そんな再建築不可物件を今後持ち続けていると、どうなるのでしょうか?
大きく分けると、7つのリスクが考えられます。
2、メンテナンスなどの維持費が重くのしかかる
3、近隣住民からの苦情や損害賠償のリスク
4、税金を払い続けなければならない
5、特定空き家に指定される恐れがある
6、更地にすると税金が跳ね上がる
7、「4号特例の縮小」でリフォームできない
1、資産価値が下がり続けて売れづらくなる

再建築不可物件は、持ち続ければ持ち続けるほど資産価値が下がり続け、売れづらくなります。
理由は、中古物件は築浅であるほど需要が高く、逆に、築年数が古いほど需要はなくなっていくからです。
先ほどもお伝えした通り、再建築不可物件は最低でも築56年以上が経過しており、建物が古いため老朽化も激しいです。
今の時点でそうなのですから、これから5年、10年と年月が経過すれば、さらに劣化が激しくなり、売れづらくなることは容易に想像できます。
外壁のひび割れ、シロアリによる浸食、雨漏りなどの瑕疵(かし)はもちろん、建物の古臭さも際立ってきますので、資産価値は下がる一方です。
また、再建築不可物件は「担保価値」が付かないため、銀行の「住宅ローン」がほとんど通らないことも、売れづらい原因の一つです。
2、メンテナンスなどの維持費が重くのしかかる

再建築不可物件を持ち続けると、激しい老朽化によってメンテナンスなどの維持費用が重くのしかかってきます。
築50年以上にもなる古物件というのは、一度メンテナンスをすればそれでOKとはならず、絶え間なく維持費用がかかる場合が多いです。
特に、人が住んでいない空き家の場合は、その劣化スピードも早くなります。
大きな原因は、家屋の換気がされないことによって湿気などが滞り、シロアリなどの害虫が巣食ったり、カビやダニ等が大量に発生してしまうためです。
また、キッチン・お風呂・トイレなどの上下水道を使用しないことによって、ゴキブリやネズミが住みつくことも、空き家の劣化を加速させる要因と言えます。
さまざまな悪条件が重なることで、維持費が多額になってしまう再建築不可の空き家・・・
ちなみに、遠方の空き家だからという理由で、部屋の換気やポストの郵便物整理などを業者に依頼すれば、その費用もかかることは知っておいた方が良いでしょう。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
3、近隣住民からの苦情や損害賠償のリスク

「再建築不可物件にお金をかけたくないから」と、ろくにメンテナンスもせずに放置すると、近隣住民からの苦情が市町村役場に入りやすくなります。
築年数が古い再建築不可物件は、朽ちてボロボロになっているケースも珍しくありません。
そのため、景観を損ねる、不衛生、怖い等の理由から、劣化した建物の補修や、生い茂った草木の伐採を求められるケースが多いのです。
また、物件が木造なら火災になりやすく燃え広がりやすいのも不安材料。
不審者が出入りするかもしれない等のリスクも考えなければなりません。
上記のようなマイナスの材料がたくさんあるため、安全上の理由で近隣住民からのクレームが出やすくなるのです。
もちろん、すぐに対応できれば問題ないのですが、遠方にある物件を相続した場合などはなかなかそうもいかず、足が遠のいてしまうことも多いでしょう。
しかも、そんな状態を長期にわたって放置すれば、さらに建物の経年劣化が激しくなる事が考えられます。
仮に、台風などで外壁が剥がれ、近隣の家に損害を与えたり、住民や通行人にケガなどを負わせようものなら、損害賠償を請求される恐れがあります。
法的にも大きな責任問題にも発展してしまう可能性があるため、所有者は気が休まらず、不安な日々を過ごすことになってしまうのです。
4、固定資産税、都市計画税を払い続けなければならない


再建築不可物件を持ち続けると、税金もバカになりません。
言うまでもなく、不動産の所有者には「固定資産税」や「都市計画税」などの納税義務があります。
残念ながら、その物件に住んでいようがいまいが、運用していようがいまいが関係なく、税金の支払いだけは続けなければなりません。
数か月や1年くらいならまだしも、再建築不可物件を何年も何十年も所有していると、累積赤字は相当な金額になるはずです。
特に、住むわけでもなく運用しているわけでもなく、ただ所有しているというだけで、毎年高い税金を払い続けなければならないのは、かなりの経済的な痛手と言えるでしょう。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
5、特定空き家に指定される恐れがある

再建築不可物件であるなしに関わらず、空き家を放置していると「特定空き家」に指定される場合があります。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」によると、「特定空き家」とは、以下の4つの内容が該当する空き家と定められています。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空き家」に指定されると、それまで居住用の土地ということで受けられていた固定資産税等の優遇措置が、翌年から受けられなくなってしまいます。
そのため、支払う固定資産税がおよそ6倍に跳ね上がることもあり、さらに経済的マイナスは拡大してしまいます。
しかも、「特定空き家」に指定されると、自治体から助言や指導、勧告や命令が出されることがあるという事実は知っておいた方が良いです。
行政代執行により、空き家が強制的に解体され、かかった費用が請求されるという最悪のケースになる場合も想定しておかなければならないのです。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
6、更地にすると税金が跳ね上がる
建物が古くて老朽化が激しいから売れない・・・なら、いっそのこと解体してしまえ!とでも言わんばかりに、再建築不可物件を更地にする人がいらっしゃいます。

ですが、これも居住用の土地としての優遇が受けられなくなるため、固定資産税がおよそ6倍に跳ね上がります。
しかも、再建築不可物件は新しく建物が建てられないため、更地の方が売れにくくなります。

何百万円も解体費用をかけて更地にした結果、税金は跳ね上がるし、さらに物件が売れにくくなるなんて、何も良いことはないのね。
7、「4号特例の縮小」でリフォームできない
最後は、2025年4月からの法改正による問題です。
この法改正は、再建築不可物件の所有者にとっては、かなり厳しいものになりそうです。
「4号特例」とは、現行の建築基準法の「4号建築物」において、都市計画区域以外で建築士が建築した、あるいは建築士が設計した通りに建てられたことを確認した建物なら、「建築確認申請」が免除となる特例措置のこと。
4号建築物とは、以下の条件を満たす建物のことです。
【4号建築物】
●木造・・・2階建以下で、延べ床面積500㎡以下、軒高9m以下、高さ13m以下の建物
●木造以外・・・平屋で、延べ床面積が200㎡以下の建物
つまり、一般的な木造二階建てや、木造平屋建ての多くが、「4号建築物」と考えれば分かりやすいでしょう。
現行法では、都市計画地域などに該当する場合は「建築確認申請」が必要でも、それ以外(かなり広い範囲)の地域であれば、免除してもらえます。
そのため、今までは「4号特例」のおかげで、多くの再建築不可の住宅をリフォームすることができ、売却がスムーズに運ぶこともありました。
ところが、2025年4月の法改正で4号建築物が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」の2つに分かれることになったのです。
・木造2階建て
・延床200㎡を超える木造平屋建て
※全ての地域で建築確認と検査が必要となり、免除の対象外となる
・延べ面積200㎡以下の木造平屋建て
※都市計画区域等内には建築確認と検査が必要だが、それ以外の場所なら免除の対象になる
つまり、2025年4月からは「4号特例」が大きく縮小され、「新2号建築物」に分けられた建築物は、建築確認申請が免除される特例がなくなるということです。
今まではリフォームすれば活用できた再建築不可物件でも、建築確認申請が必要になることで、リフォームできない物件が増えてしまうのです。
以上のように、再建築不可物件は、ただでさえ多大な労力と費用がかかるにも関わらず、その状況は良くなるどころか、年々厳しくなっていると言わざるを得ません。
そのため、今のうちに思い切って売却するのも一つの選択肢です。
「訳あり物件」を専門とする買取業者なら、独自販売ルートやノウハウを持っているため、驚くような高額買取が実現することも珍しいことではありません。
査定は「完全無料」なので、再建築不可物件の活用に悩んでいる方は利用してみてくださいね!
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
【プロ直伝】訳あり物件を最高値で売却するための最強売却術

「私の訳あり物件を、できるだけ高く買い取って欲しい!」
あなたもそう思いますよね?
誰だって、所有している不動産を少しでも高く売却したいのは、当たり前です。
しかし、街角の不動産業者に頼んだところで、訳あり物件は断られるか、買い叩かれるのが関の山・・・
そこで、専門の買取業者の出番となるわけですが、「一番高く買ってくれる業者」は外からでは分かりません。
では、どうしたらいいのか・・・?
それは、ズバリ!
複数の業者から見積もりを取る方法が一番です!しかもスマホからカンタンに。
これから、当サイトが推奨する「最強・訳あり物件売却術」をお教えします!
実際にこの通りに行動を起こせば、あなたの訳あり物件が、最高額に近い価格で売却できる可能性が高まります!
3ステップで終わるので、とてもカンタンですよ。
複数の買取店から見積りを取るのが、高値売却の最大のコツ!

・スマホを使って、自宅にいながら誰でもカンタンにできますよ!
選ぶ買取業者によって、買ってくれる価格に差がつくことは本当によくあるんです!
なぜなら、それぞれの業者ごとに得意・不得意があるからです。
だからこそ、複数の「専門買取業者」の中から見積りを取得して比較することが大切です。
あなたは見積り金額を比較して、もっとも高値をつけた業者に売却すればいいだけです!
自宅にいながらスマホ(又はPC)1つで無料査定を依頼してみましょう!
実際の査定額を公開!
専門の買取業者なら高く売れる!
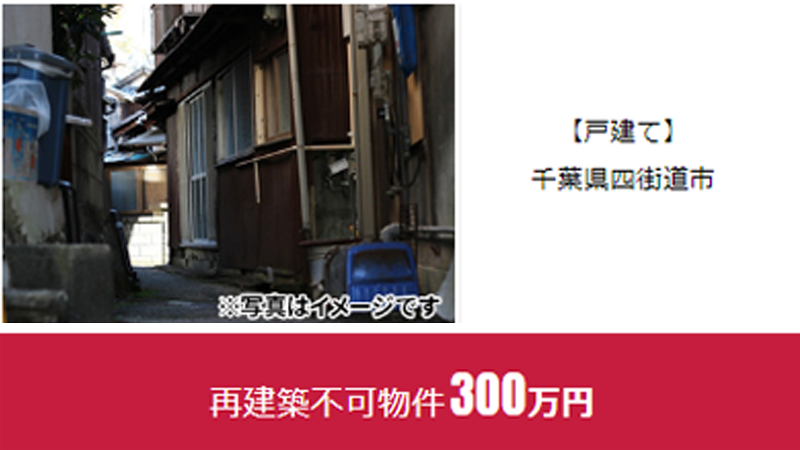


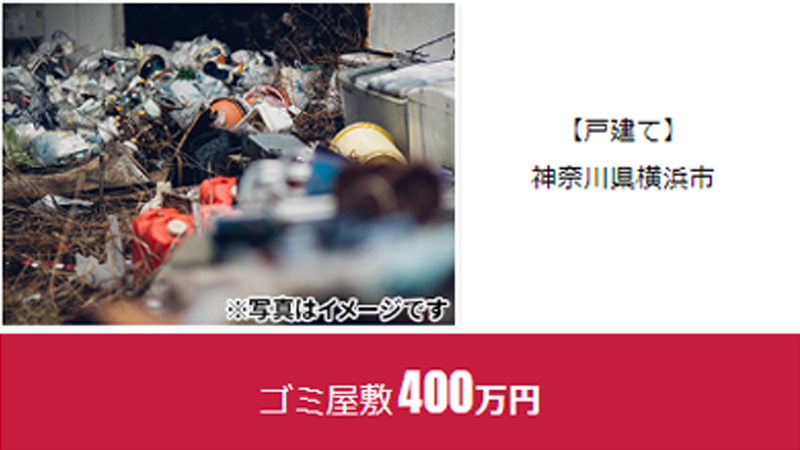

訳あり物件を最高値で売る!最強3ステップを公開!

「訳あり物件」を最高価格で売却するには、以下の3ステップでOKです。
ステップ2:「無料査定」を依頼する
ステップ3:「買取価格」を比較して、一番高いところに売却する
ステップ1:訳あり物件に強い専門の買取業者を複数ピックアップ
まずは、訳あり物件に強い専門の買取業者を複数ピックアップしましょう。
訳あり物件に強い専門の買取業者を選ぶときは、「訳あり」の買取実績がどれだけ豊富なのかに着目して選びます。
「訳あり」もいろいろありますが、分かりやすい目安として「事故物件」の実績が豊富な業者なら、しっかりとしたノウハウを持っていると考えてまちがいないです。
さらに、弁護士や司法書士、土地家屋調査士等のパイプがしっかりしていれば法的処理もスムーズで、スピーディーかつ高額買取の可能性が高いです。
当サイトでは、以下3社の「無料査定」を使います。
ステップ2:「無料査定」を依頼する
上記サイトで、無料査定を依頼します。
どのサイトも30秒~1分くらいで入力は完了します。カンタンですよ。
ステップ3:買取価格を比較して、一番高いところに売却する
複数の業者から見積りを取得したら買取価格を比較しましょう!
単純に見積額の高い業者を見つければOKです。
なお、もしも交渉するのなら、他のサイトの価格は一切言わないことが重要です。
単純に無料査定の査定額を比較し、一番高い会社を選ぶことをおすすめします。
ちなみに、価格差がそれほど大きくない時は、交渉するのもアリですが、その場合は営業マンが誠実かどうかをしっかり見て決めましょう。
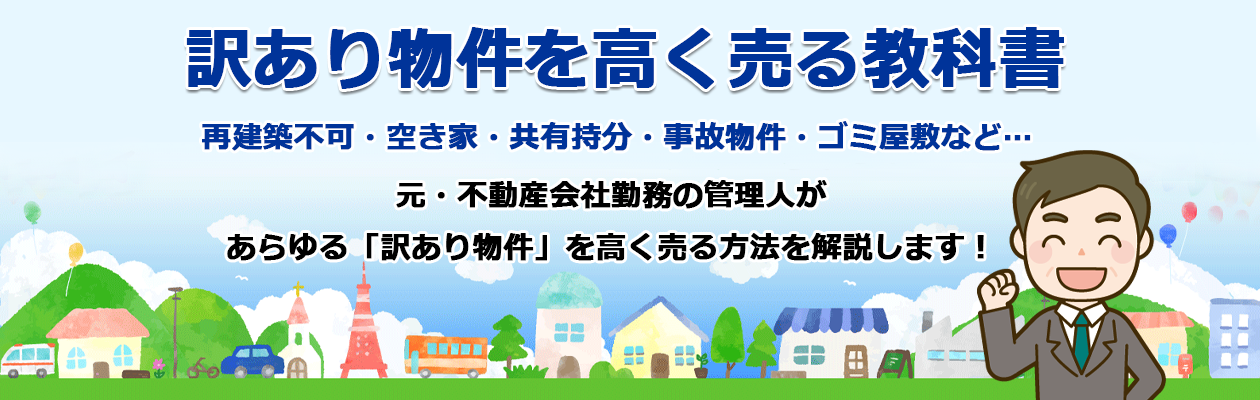
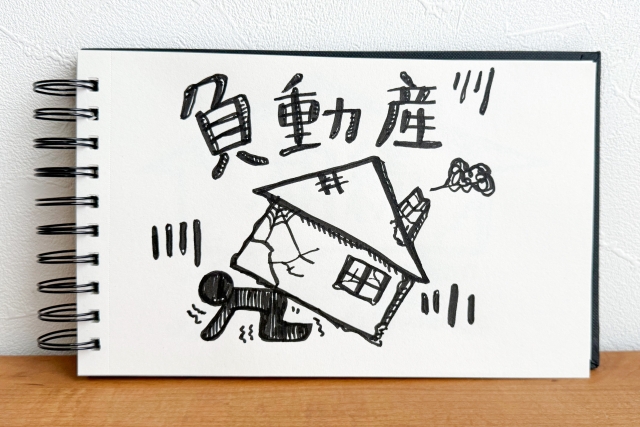


コメント