
古い家を所有していると「もし建物が倒壊したらどうしよう…」と不安を感じる方は多いと思います。
特に、再建築不可物件が倒壊すると、建て替えができないために思わぬトラブルや経済的な負担につながる恐れがあります。
実際にどんなリスクがあるのか、そしてどのように対応すれば安心できるのかを知っておくことは、所有者にとって大切な備えです。
今回は、再建築不可物件の倒壊リスクや注意点、具体的な解決方法をわかりやすく解説します。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
再建築不可物件の倒壊リスクが高い理由

再建築不可物件は、通常の住宅よりも倒壊の危険性が高いといわれています。

その理由について、5つに分けて解説します。
1. 建物が老朽化して耐震性が低下している
再建築不可物件の多くは築年数が古く、すでに耐用年数を大きく超えているケースも多いです。
- 柱や梁の劣化
- 基礎のひび割れ
- 屋根や外壁の損傷
などが進むと、建物全体の強度が低下し、地震や強風への耐性が著しく弱まります。
特に、昭和56年以前の建物は「新耐震基準」を満たしておらず、大地震時に倒壊する可能性が高いと指摘されています。
定期的に補強や修繕を行えば一定の延命は可能ですが、再建築不可物件では投資判断が難しいため、老朽化が放置されがちです。
そのため、災害時に大きな被害を受けやすくなってしまうのです。
2. 建築基準法に適合していない構造が多い
再建築不可物件は、接道条件や敷地条件を満たしていないことが多く、建築基準法に適合していないまま使用されている場合があります。
こうした建物は、安全基準をクリアしていないため、地震や火災の際に被害が拡大しやすいのが特徴です。
また、違法建築に近い状態で「増築」や「改築」が行われている物件もあり、建物のバランスが悪く倒壊リスクをさらに高めます。
法律上、解体しても再建築が認められないため、本格的な改修が行われず、現状のまま使用されていることも少なくありません。
結果として、安全性に不安を抱えたまま存在してしまうのです。
関連記事

3. 修繕や建て替えが困難で放置されやすい
再建築不可物件は「建て替え」ができないため、所有者が思い切った修繕や改築に踏み切りにくい傾向があります。
多額の費用をかけても資産価値が上がらず、金融機関からの融資も受けにくいため、結果的に「修繕しないまま放置」という選択になりがちです。
屋根の破損や外壁の崩落、基礎のひび割れを放置すると劣化が加速し、倒壊のリスクがさらに高まります。
また、管理が難しいために「空き家化」してしまい、誰も住んでいないことで傷みが進むという悪循環が起こりやすい点も問題です。

「建て替え不可」という制約が、建物の寿命を縮めていると言えそうね。
4. 接道義務を満たさず緊急時の対応が難しい
現行の建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ建築は認められません。
しかし、再建築不可物件はこの接道義務を満たしていないため、袋地や旗竿地にあるケースが多いのです。
その結果、地震や火災が発生した際に消防車や救急車が近づけず、消火や救助が遅れる可能性があります。
また、倒壊や延焼の被害が拡大しやすく、近隣住民を巻き込む危険性をはらんでいるケースも多いです。
「緊急時に対応が難しい立地条件」は、倒壊後の被害を大きくしてしまう要因となっています。
関連記事

5. 空き家化しやすく管理不足になる
再建築不可物件は売却が難しく、相続後も使い道がないため空き家になりやすい特徴があります。
人が住まなくなると換気や掃除がされず、湿気や害虫の発生、木材の腐食が進み、老朽化のスピードが加速します。
管理が行き届かなくなることで倒壊リスクはさらに高まり、「生い茂った雑草」や「不法投棄」などによって近隣トラブルにもつながります。
所有者が遠方に住んでいる場合は、管理がほぼ放置されることも多く、建物の安全性が著しく低下してしまうのです。
このように、空き家化が倒壊リスクをさらに押し上げる要因になっているのです。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
再建築不可物件が倒壊した場合に起こる「4つのリスク」

再建築不可物件が倒壊すると、所有者には大きな負担や不利益がのしかかります。

ここでは、倒壊後に直面する代表的な「4つのリスク」を解説します。
1. 更地にすると固定資産税が高くなる
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。
しかし、建物が倒壊して更地になってしまうと、この特例が外れてしまいます。
その結果、「固定資産税」が最大で約6倍に跳ね上がることもあるのです。
例えば、年間10万円だった税額が一気に60万円近くに増えるケースがあるわけですから、たまったものではありません。
利用価値の乏しい土地なのに税負担だけが重くのしかかるため、所有者にとっては大きな経済的ダメージとなります。
なお、このリスクは倒壊後すぐに現れるため、早めに対策を検討しておく必要があります。
2. 売却が極めて難しくなる
倒壊した「再建築不可物件」は、買い手がほとんど見つからないのが現実です。
なぜなら、建て替えができないため、一般的な住宅需要に応えることができず、流通市場から敬遠されてしまうからです。
更地にしても、再利用方法が限られるため、投資目的の購入も期待できません。
仮に買い手がついたとしても、相場より大幅に安い価格での売却となる可能性が高いです。
こうした事情から、倒壊後に売却を考えるのは非常に難しく、所有者の負担をさらに重くしてしまいます。
関連記事

3. 近隣に被害を与えた場合の損害賠償リスク
老朽化した建物が倒壊すると、瓦礫や外壁が近隣の家や道路に被害を及ぼすことがあります。
その場合、所有者が「損害賠償責任」を問われる可能性が高いです。
たとえば、倒壊によって隣家の屋根を壊したり、通行人にケガを負わせたりすれば、多額の賠償金を求められます。
裁判沙汰に発展するケースも多く、その場合は精神的にも大きな負担を抱えることになります。
「知らなかった」「想定外だった」では済まされないため、管理責任を果たしていなかった場合は特に厳しく追及されます。
このリスクは所有者にとって最も深刻な問題の一つといえます。
4. 資産価値が大幅に下落する
倒壊した再建築不可物件は、資産としての価値を大きく失います。
なぜなら、建物としての利用価値がなくなり土地も再建築できないため、評価額が大幅に下落してしまうからです。
金融機関からの担保価値もゼロに近くなるため、ローンを組むことも困難です。
仮に、貸し出しや活用を検討しても、需要が乏しく収益性は低いのが現状です。
結果として、維持費と税負担だけがかかり続け、資産ではなく「負動産」となってしまうのです。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
倒壊リスクを回避するための対策方法

再建築不可物件は放置してしまうと倒壊の危険が高まり、所有者に大きな負担を与えます。
そのため、事前に対策を取ることは大切です。

ここでは、倒壊リスクを回避するための「3つの方法」を紹介します。
1. 耐震補強や修繕で安全性を確保する
最も基本的な対策は、建物を補強して倒壊リスクを減らすことです。
特に、昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた住宅は、大地震での倒壊可能性が高いため「耐震補強」が効果的です。
- 基礎の補強
- 柱や梁の補強
- 屋根の軽量化
などを行えば、揺れへの耐性が向上します。
また、外壁のひび割れや雨漏りといった小さな劣化も放置せず修繕することで、老朽化の進行を遅らせることができます。
ただし、老朽化が激しい物件の場合は、費用がかなりかかってしまうことを覚悟しておかなくてはなりません。
2. 火災保険・地震保険に加入しておく
災害は予測できないため、保険で備えることも重要です。
火災保険に加入しておけば、火災や風災による被害に対応でき、地震保険は地震による倒壊や半壊に備えられます。
もちろん、再建築はできませんが「修繕費用」や「後片付け費用」の負担を軽減できます。
また、隣家に火災が延焼した場合や、地震で大規模な修復が必要になった際にも、保険金で対応できれば経済的なダメージを抑えられます。
管理責任を果たすという意味でも、保険加入は選択肢の一つとして持っておくと良いでしょう。
関連記事

3. セットバックや隣地購入で「再建築可能」にする
法的に建て替えが認められない最大の理由は「接道義務」を満たしていないことです。
この場合、道路幅を確保するために敷地の一部を後退させる「セットバック」を行う方法があります。
あるいは、隣地を一部購入して2m以上の接道を確保できれば、建築基準を満たし再建築が可能になります。
ただし、この方法は「隣地所有者」との交渉や、セットバック費用が発生するため、実現のハードルは高いのが現実です。
それでも、再建築が可能になれば、物件の資産価値は大きく回復するため検討する価値はあるかもしれません。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
倒壊した再建築不可物件を手放す方法

再建築不可物件が倒壊してしまった場合、「固定資産税」や「管理責任」だけが残るため、できるだけ早く手放したいという方も多いでしょう。

そこで、倒壊した再建築不可物件を手放す方法を6つ紹介します。
1. 更地にして土地のみで売却する
倒壊した建物を解体して更地にすれば、最低限「土地」として売却することが可能です。
立地が良い物件なら、再建築不可の土地でも買い手がつくかもしれません。
ただし、多くの場合、再建築不可のままでは住宅需要がなく、買い手は限られます。
資材置き場や駐車場として利用できるケースはありますが、相場より低価格での取引になりやすいのが実情です。
解体費用も所有者負担になるため、費用対効果をよく検討してから選択する必要があります。
2. 隣地所有者へ売却して活用してもらう
隣地の所有者にとっては、土地を買い足すことで接道条件を満たし「再建築可能」にできるメリットがあります。
そのため、一般市場よりも高い価格で売却できる可能性があります。
ただし、交渉がスムーズにいくかどうかは相手の事情次第で、必ず成立するわけではないということは肝に銘じておきましょう。
近隣との関係性が良好であれば、まずは提案してみる価値のある方法です。
3. 自治体や公共団体への寄付を検討する
利用価値の低い土地は、自治体や公共団体に寄付できる場合があります。
ただし、地域の道路拡張や公共施設の整備などに役立つこともある反面、受け入れ自体が難しいケースも多いです。
寄付が成立すれば「維持費」や「税負担」から解放されますが、必ずしも受理される保証がないため、事前に確認が必要です。
4. 相続放棄で所有権を手放す
相続によって取得した物件で維持が難しい場合は、相続放棄を選ぶこともできます。
相続放棄をすれば所有権を引き継がず、固定資産税や管理義務からも解放されます。
ただし放棄できるのは相続開始から3か月以内が原則で、他の財産もまとめて放棄することになる点に注意が必要です。
5. 不動産管理会社に処分や活用を依頼する
自分で処分方法を決められない場合、不動産管理会社に依頼する方法もあります。
管理会社は物件の調査や活用方法を提案し、必要に応じて処分の手続きを代行してくれます。
ただし費用が発生するため、コストと成果のバランスを確認してから利用することが大切です。
6. 訳あり物件専門の不動産買取業者へ売却する
倒壊した再建築不可物件を手放す方法の中で、もっとも現実的でスピーディーな解決策は、訳あり物件専門の不動産買取業者に売却することです。
一般的な不動産会社では建て替えができない土地は扱いにくく、買い手が見つからないケースがほとんど。
しかし、専門業者なら、再建築不可・倒壊後・老朽化の進んだ物件でも独自のノウハウで活用できるため、高値で買い取ってもらえる可能性が高いのです。
さらに、仲介を通さず直接買取を行うため、仲介手数料も取られません。
査定から現金化までが早く、最短で即日〜数週間で手元に資金が入ります。
数ある方法の中でも、リスクを最小限に抑え、確実に不動産を処分できるのがこの方法です。
査定は「完全無料」なので、まずは気軽に相談してみると良いでしょう。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
再建築不可物件は倒壊前の早期対応が重要

再建築不可物件は、倒壊してしまうと売却も活用も一気に難しくなります。
そのため「いつ手放すか」「どの業者に依頼するか」という判断がとても大切です。

そこで最後に、売却の最適なタイミングと、失敗しない業者選びのコツを解説します。
1. 売却に最適なタイミングとは?
再建築不可物件は、老朽化が進む前に売却するのがもっとも有利です。
理由は簡単で、建物が倒壊すれば建て替えができず、更地にしても需要が大幅に下がるからです。
築年数が浅いうちなら、最低限のリフォームや賃貸利用を検討する買主も現れる可能性があります。
また、固定資産税の軽減措置が適用されている間に売却すれば、買主にとってもメリットがあるため、交渉が進みやすいのも特徴です。
「もう使わない」と感じた時点で早めに動くことが、後悔を防ぐ最大のポイントといえるでしょう。
2. 業者選びのポイントと比較のコツ
業者選びを誤ると、売却が長引いたり価格が大きく下がったりします。
そのため、まず重要なことは、再建築不可物件や事故物件など「訳あり不動産」を専門に扱っている業者を選ぶことです。
通常の不動産会社では取り扱いが難しく、断られるケースも少なくありません。
複数の業者に査定を依頼し、買取実績や契約条件を比較することも欠かせません。
スピードを重視するなら即時買取型、価格を重視するなら交渉力のある業者、と目的に合わせて選ぶのがコツです。
信頼できる専門業者を見つけることで、安心して早期売却を実現できますよ。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
まとめ|再建築不可物件は「倒壊前の売却」が最善策

再建築不可物件は、老朽化や地震・火災によって倒壊すると、建て替えができず、税負担や管理リスクだけが残ってしまいます。
更地にしても固定資産税が高くなり、売却は難しく、資産価値は大きく下がるのが現実です。
そのため、最も重要なのは「倒壊する前に動くこと」です。
耐震補強や保険加入といった備えも必要ですが、根本的な解決策は早期の売却にあります。
特に、再建築不可や倒壊物件の取り扱いに慣れた「訳あり物件専門の不動産買取業者」へ相談すれば、確実かつスピーディーに問題を解決できます。
もし所有している再建築不可物件に不安を感じているなら、まずは信頼できる専門業者へ査定を依頼し、最適な解決策を探ってください。
放置して負担を抱える前に、今すぐ動き出しましょう。
\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら
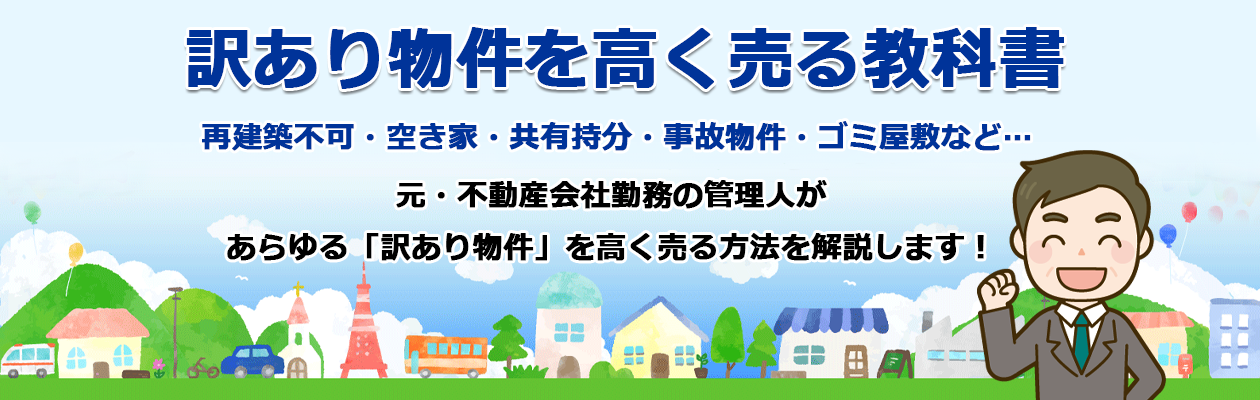



コメント